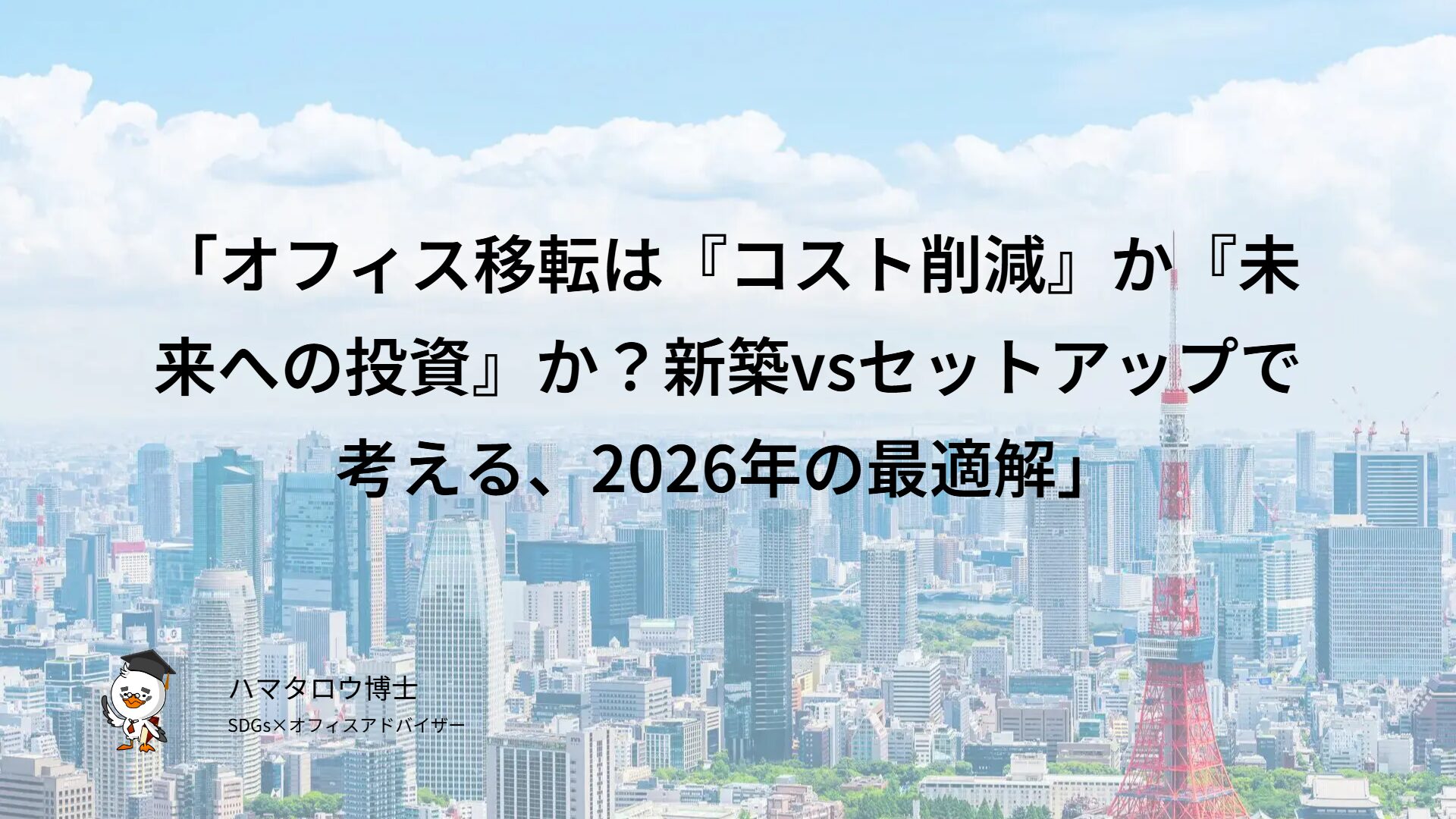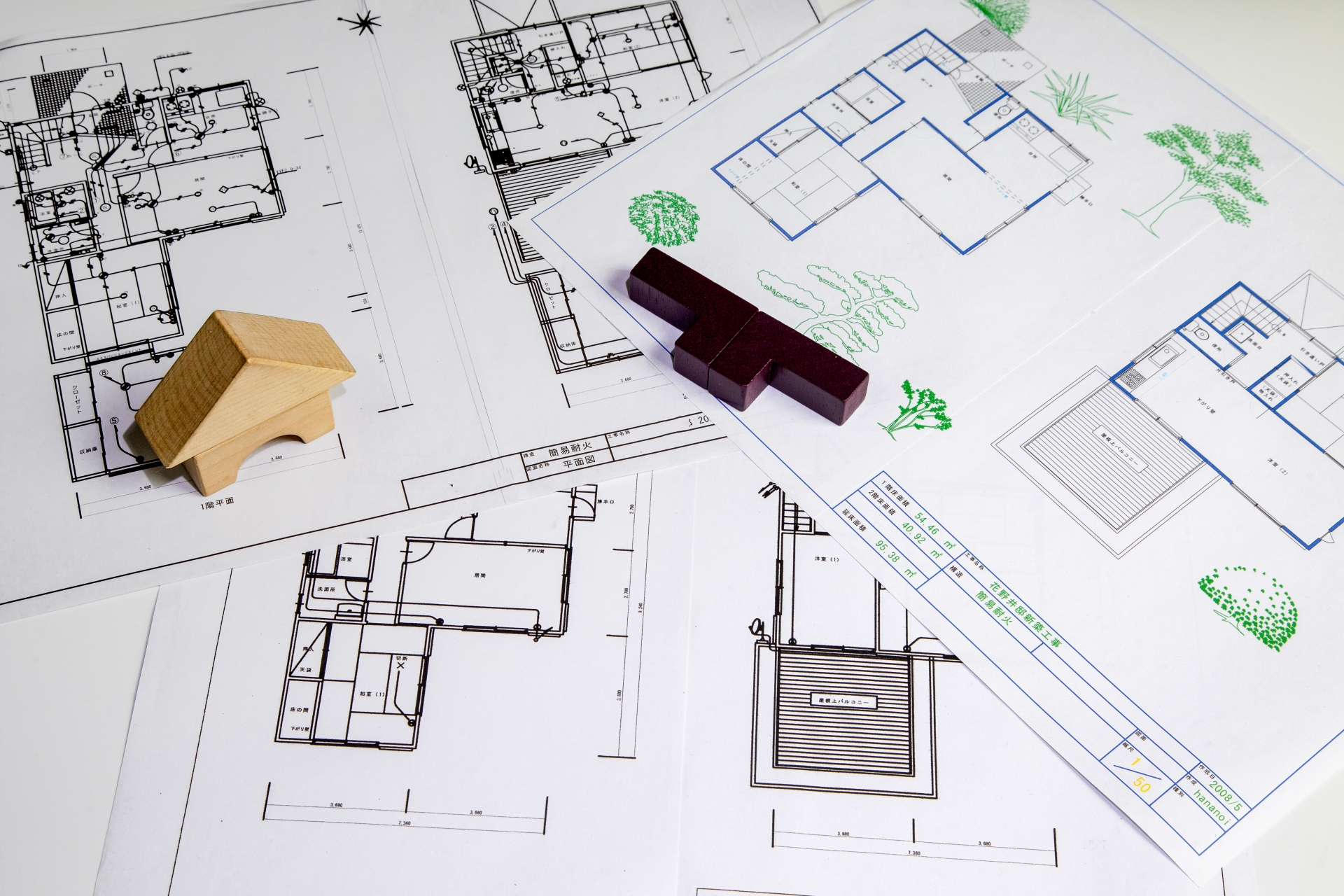オフィス移転・開設で役立つ!初めてでもわかる不動産用語まとめ【保存版】

オフィスの移転や新規開設を検討し始めたとき、必ずぶつかるのが「不動産用語の壁」。
物件検索サイトや不動産会社のチラシ・営業担当者との会話の中で、「スケルトン」「OAフロア」「フリーレント」など、普段は耳慣れない言葉がたくさん登場します。不動産の専門用語を正しく理解していないと、物件比較の判断がつかなかったり、契約内容に見落としが出たりすることも。
そこで本記事では、オフィス物件を探し始める方に向けて、基本かつ重要な不動産用語をわかりやすく解説します。
事業用不動産用語解説
貸室内関連
OAフロア(フリーアクセスフロア)
床下に配線スペースを設けた構造のことで、LANや電源などを自由に配線できます。配線を床下収納できるのでレイアウトがスッキリする上、レイアウト変更や機器追加にも柔軟に対応でき、現代では多くのオフィスに採用されています。OAフロアの高さ(床下の厚み)は50mm、100mmタイプのものが一般的です。後付けで設置すると天井高が低くなってしまうデメリットもあります。
タイルカーペット
正方形にカットされたカーペットのこと。事務所で利用するタイルカーペットは 50cm×50cmのサイズが一般的です。汚れた部分のみを交換できるため、清潔感を保ちやすく、コスト面でも優れています。デザイン、色、毛足の長さなど種類が豊富です。
Pタイル
主に塩化ビニル樹脂などを使った約30cm×30cmのタイル上の床のことで、別名プラスチックタイルとも呼ばれる、固い床材になります。耐久性があり、水や汚れにも強いため、オフィスの他、クリニックや店舗などでも利用されることが多いのが特徴です。
スケルトン
内装が施されていない「骨組み状態」の物件。自由に内装を設計できる一方、内装工事などの初期費用がかかります。
天井高(天高)
貸室内の床から天井までの高さのことです。開放感のある空間や空調効率に関わる要素です。貸事務所において、天井高が低く感じられず、高くも感じられない高さは、約2,500mmです。オフィスビルの場合は、天井に梁があることも多いので、執務室全体の天井高が一定であるとは限らないため注意が必要です。
グリッドシステム天井
照明・空調・スプリンクラーなどが均等に配置され、天井構造が整っている形式。従来型の天井は、下地にボードを貼り、設備機器は後から切り込みセットする方式であるのに対して、システム天井は、天井面のランナーや枠にボードや設備機器をはめ込みセットする方式です。機能性や適応性が高いことが特徴的で、レイアウト変更にも柔軟に対応できます。
ダイレクトイン
エレベータホールがなく、エレベーターを降りるとすぐに貸室内という造りのオフィスビルのこと。ビルの共用部を経由せず、直接専有区画に入れる構造になっています。ドアがなく、いきなり室内となるため、来客者の受付スペースを室内に設置する必要があります。
床荷重
1㎡あたりの床が耐えられる荷重の限界値のこと。重量物を置く予定がある場合には確認が必要です。オフィスビルの床荷重は、300㎏/㎡が一般的です。
ヘビーデューティーゾーン
サーバーや書庫など荷重が必要な施設を置く場合を想定し、床の一部分の床荷重を補強しているエリアのこと。500㎏/㎡~1,000㎏/㎡程度の床荷重に耐えられる造りとなっています。
個別空調
専有部ごとに冷暖房を調整できる空調方式。パッケージ方式とも呼ばれます。時間外の稼働や細かな温度設定が可能で、コスト管理にも便利です。
セントラル空調
ビル全体またはフロア単位を一括で冷暖房管理する方式。中央方式とも呼ばれます。あらかじめ運転時間が決められています。時間外で空調を動かしたい場合は、時間外空調費等を負担することで対応が可能な場合がほとんどです。しかし個別空調と異なり、ゾーンごとの空調稼働や温度調節ができないため、残業等で夜遅くまでオフィスを使用する企業にとっては使い勝手が悪いということも考えられます。一方で、ビルで定められたコアタイムの空調費は共益費に含まれているので、時間外勤務がない場合には、セントラル空調の方がコストメリットが出る可能性があります。
セットアップオフィス
会議室や什器備品類などがあらかじめ整った状態で貸し出されるオフィスのこと。内装工事やレイアウト設計などが不要なため、入居後すぐに業務を開始でき、時間とコストを大幅に削減できる点が大きなメリットです。デザイン性や利便性にも優れた物件が多く、スタートアップや支店開設を検討する企業に特に支持されています。
なお、セットアップオフィスは「居抜きオフィス」と異なり、あらかじめ貸主が汎用的に設計・施工して提供している点が特徴です。
居抜きオフィス
前の入居企業が使用していた内装・什器・設備などを残した状態で、そのまま引き継ぐ形で契約のことです。たとえば、会議室の間仕切りや照明、場合によっては机・椅子までが残されているケースもあり、内装工事費用や工期を大幅に削減できるというメリットがあります。通常のオフィス契約では、入居時に内装工事、退去時に原状回復工事が必要になりますが、居抜き契約ではこうした工事が最小限で済むため、スピード感を重視した移転が可能となります。
一方で、レイアウトやデザインが自社イメージに合わない場合や、設備の経年劣化リスクなどの注意点もあるため、内覧時の確認や契約条件の精査が重要です。また、造作譲渡契約(※内装・什器の引き継ぎに関する契約)や原状回復範囲についても、事前の取り決めが必要になることが多いため、不動産会社に相談しながら進めることをおすすめします。
内覧(内見)
貸事務所を探す際に、募集している物件を見学に行くことです。一般的には建物の外観のみならず、室内を見に行くことを指します。貸事務所の場合は、内覧(内見)時にビルオーナーや管理会社などが立ち会うことが多いので、連絡してすぐに室内を見れることは少なく、日程の調整が必要になります。広さや設備、雰囲気を確かめるために、入居前には必ず行いましょう。また、最近では「オンライン内覧」や「360度パノラマ動画」に対応する仲介業者も増加しています。

契約関連
フリーレント
契約開始後、一定期間賃料が免除になる契約形態。初期費用を抑えたい企業に人気の条件です。ただし注意点として、フリーレント期間中であっても「共益費(管理費)」は別途発生するのが一般的です。また、フリーレント契約には「一定期間の解約禁止条項」や「短期解約時の違約金発生条件」が設けられているケースが多いため、契約前に詳細条件をよく確認しておくことが重要です。
共益費(管理費)
賃料とは別に支払われる費用のことで、エントランスやトイレ、エレベーターなど共用部の水道光熱費、清掃費、修繕費、保安管理費、冷暖房空調費等に使われています。管理費と称されることもあります。
預託金
賃借人(借主)が賃貸人(貸主)に対して、賃料等の債務に対する担保として、あらかじめ預託する金銭のことです。敷金や保証金を総称した名称です。原則として退去時に返還されますが、原状回復費用などが差し引かれる場合があります。
重要事項説明(重説)
契約に先立って、不動産会社が物件の内容や契約条件を説明する義務的手続き。宅地建物取引業法第35条により、宅地建物取引業者(不動産屋)に義務づけられています。不動産関係者は、よく省略して重説(じゅうせつ)呼びます。対面で紙の書類に署名・捺印をするのが主流でしたが、近年では「WEB重説(オンライン重説)」にも対応する業者が増えています。
解約予告
現在借りているオフィスの貸主または管理会社に対して退去をする旨を通知をすることです。貸事務所の場合、解約予告は6ヶ月前や3ヶ月前という期間設定が一般的です。契約書に「文書にて通知する旨」を記載されていることが多いので確認が必要です。解約予告を通知すると、その期間内に什器類等の撤去はもちろん、原状回復工事を完了させ、賃貸借室を返却する必要があります。
PM(プロパティマネジメント)
不動産の所有者に代わり、運営・管理を行う業務全般。ビル管理会社やPM会社が担うことが多いです。具体的な業務としては、建物の物理的な維持・管理業務、テナントの誘致、交渉、賃貸借業務の代行、賃料・共益費などの請求・回収、トラブル時の対応などがあげられます。
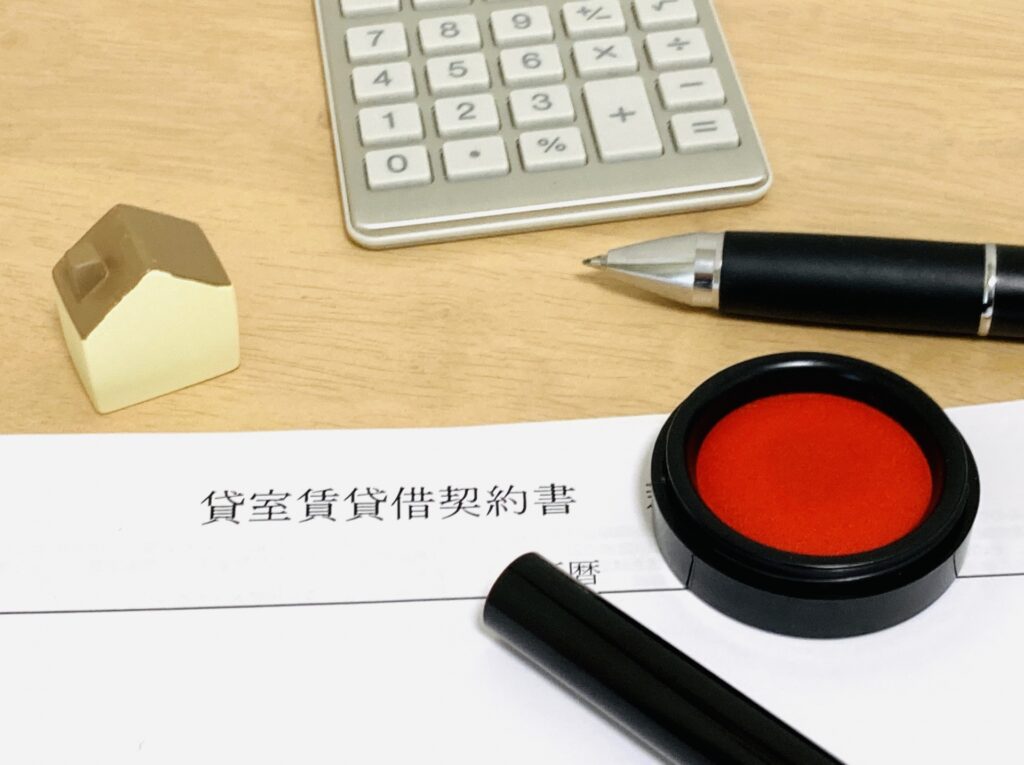
設備関連
PS(パイプスペース)
給水管・排水管などの生活排水に関わるパイプ設備が通っているスペースのことを指します。貸事務所の募集資料等の図面上に「PS」と表記されています。
EPS(エレクトリック・パイプ・スペース)
電気配線とその配線を通す配管を収納しているスペースのことを指します。貸事務所の募集図面上には、EPSと表記されます。
トイレ室外男女別・室内男女共用
トイレの入口が室内から繋がっているか、室外である廊下などから繋がっているかの違いになります。大型ビルや高層オフィスビルの場合には、トイレ室外男女別が一般的です。入居後の快適性に直結するポイントです。
バリアフリー
高齢者や障がいのある方をはじめ、誰もが安全・快適に利用できるように、物理的・心理的な障壁(バリア)を取り除く設計や環境のことを指します。具体的には、段差がなくスロープが設置されている、車椅子で出入りしやすい自動ドア・エレベーター、多目的トイレなどの設備が挙げられ、これらは「バリアフリー対応物件」とされます。

ビルの構造関連
高層ビル
高層ビルに関する統一的な基準は存在しませんが、地上31m以上(おおよそ10階建て以上)の建物のことを指します。眺望の良さや防災設備の充実などが特徴です。建築基準法上では、高さが60mを超えると「超高層建築物」とされ、防火・避難・構造設計において特別な基準が適用されます。
SRC造
鉄骨鉄筋コンクリート造の略。柱や梁等の骨組を鉄骨で組み、その周りに鉄筋を配筋してコンクリートを打ち込む構造で、高層ビルなどに採用されます。耐震性等に優れています。
RC造
鉄筋コンクリート造の略。引っ張りに弱いコンクリートを補強するために鉄筋を配したコンクリートです。防音性・耐火性に優れ、中層ビルに多い構造です。
S造
鉄骨造の略。建築物の躯体に鉄製や鋼製の部材を用いる建築構造のこと。軽量で加工しやすく、建築期間が短いため、低層~中層ビルに多く採用されます。
新耐震基準
1981年(昭和56年)6月1日に施行された建築基準法の改正により導入された耐震設計の基準で震度6強程度の地震に耐えうる設計となっています。この日以降に建築確認を受けた建物に適用されますが、竣工年が1981〜1983年の物件は、旧基準で建てられた可能性があります。当時の工期は1〜2年程度のため、着工が改正前であれば完成が1983年でも旧耐震の可能性があるためです。そのため、確実に新耐震基準に準拠した物件を探す場合は、1984年以降の竣工物件を目安にするとよいでしょう。
近年では、旧耐震のビルも耐震補強を行っているケースが多く、竣工年だけでなく補強済みかどうかも選定時の重要な視点となります。
耐震構造
建物の構造(柱や梁)そのものが地震に耐えるように設計された建物構造のこと。耐震構造の建物は、 震度4から5弱の地震に対してはほぼ損傷を受けず、震度5強以上の地震に対しても倒壊を防止するレベルで造られています。多くのビルで採用されています。
制震構造
揺れを吸収する装置を建物に組み込み、建物の損傷を軽減する構造です。免震構造と比較するとコストは比較的安価です。
免震構造
建物と地盤の間に装置を設け免震層を造ることで、地震の揺れを直接建物に伝えにくくする高性能構造です。制振構造と比較するとより揺れを抑えるため、建物へのダメージや室内への被害を抑えることができますが、免震構造はコストが高いという特徴があります。
竣工
建築工事が完了することです。入居可能な状態になることを指します。
新築
竣工後、原則1年以内かつ未使用の状態にある物件を「新築」と呼びます。

安心の物件探しには正しい用語理解から
不動産用語は、慣れないと難しく感じることもありますが、一つひとつの意味を理解していくことで、自分に合った物件を効率的に見つけられるようになります。
「貸事務所ドットコム」では、東京・横浜を中心としたオフィス物件情報を豊富に掲載しており、今回紹介した用語をもとに、物件条件や設備の絞り込みも可能です。
「なんとなく探す」から「納得して選ぶ」オフィス探しへ。ぜひ活用してみてください!

「貸事務所ドットコム」とは、東京・横浜エリアの賃貸オフィスビルが簡単に探せる、オフィス探しに特化した検索サイトです。創業50年以上の不動産会社、(株)サンエスコーポレーションが運営しており、初めてオフィス物件を探されるお客様、物件探しの時間がないお客様でも直接現場に足を運ぶことなく、物件探しができるように、サイト上で分かりやすく正確な賃貸情報を掲載しています。サイト未掲載の非公開物件も多数ございますので、オフィス物件探しは、ぜひ「貸事務所ドットコム」にお任せください。